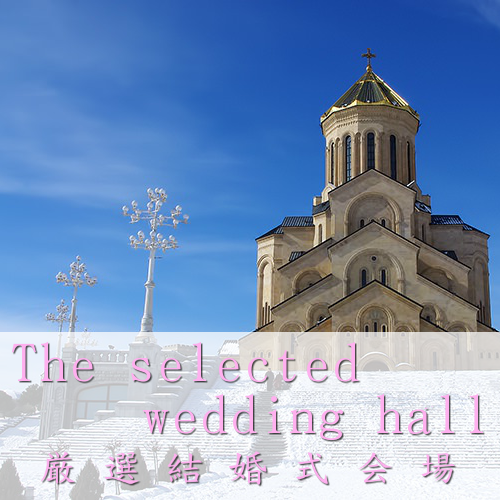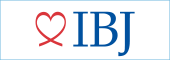神前結婚式とは
日本にしかない挙式スタイル
結婚という人生が大きな変化を遂げるタイミングで行う結婚式は、自分達の間で気持ちを引き締めるという意味だけではなく、日頃から自分達を見守ってくれている人に報告して祝福してもらうという意味もある大事なものです。
日本には海外には見られない神前結婚式という挙式スタイルが存在しています。
神前結婚式が一般の方が行うようになったのは明治時代後半から大正時代にかけてのことですが、古き好き日本のあり方を感じさせてくれる厳かな儀式を行うことで日本人としての誇りを感じさせてくれるものです。
元々は神社で行われるものでしたが、近年はホテルや結婚式場に用意されている神式祭壇を利用するケースが多いです。
神社ではなくても本格的な儀式の方法で進行されるため、日本固有の結婚式スタイルを実感できます。
神前結婚式の進行
神前結婚式は基本的にはどこで挙式を行う場合でも同様の進行の仕方になります。
あらかじめ結婚式の進行はどのようになるのかと説明をされる場合もありますが、全てを覚えていなくても大丈夫です。
斎主がきちんとアプローチしてくれますので、その指示に従って落ち着いて行動しましょう。
まずは神座に向かって左側に新婦親族、右側に新郎新婦が着席します。
神座に近い席から両親、新郎新婦の兄弟、その他の親族という順に新郎新婦との関係が深い順番に着席することになります。
仲の良い友人にも出席してもらいたいと希望する方もいますが、神前結婚式の場合は原則的に親族までが参列できることになっています。
これは、結婚式が両家の親族が揃って顔合わせをする大事な席であるという意味も込められているためです。
場合によっては友人でも参列しても良いという事もありますので、あらかじめ相談をするようにしてください。
全員着席したら修祓の儀というお祓いの儀式と献饌の儀という塩やお米をお供えする儀式を斎主が行ない、祝詞奏上では斎主が神様に二人が結婚をしたことをお知らせして祝詞と呼ばれている祝詞を読み上げてくれますので全員で起立して聞きます。
次の三献の儀では三三九度と呼ばれている新郎新婦がお酒を飲み交わす儀式を行ないます。
お酒が飲めない体質の方は無理をして飲み干す必要はなく、唇にお酒を付けるだけでも良いです。
小さな盃から中位の盃、大きな盃と3回お神酒を飲むことになりますが、これを新郎と新婦が交替して飲むことになります。
次に誓詞奏上では新郎新婦が神様に誓いに言葉を読み上げ、玉串奉奠を行なって全ての儀式が終ることになります。
最後に指輪の交換を行ない、親族で杯をかわして双方の絆を強めることになります。
これらの流れを大体頭に入れておくと実際に挙式が行われる際に慌てることがありません。
緊張をするかもしれませんが、ぜひ落ち着いて幸せな瞬間を噛みしめてください。